レコード/テーブル/フォルダ削除の実態と、データベースファイルサイズ削減の手順
まずはレコード削除とデータベースファイルサイズ削除の違いについて見てみましょう。
レコード削除:
・DELETE文やプリザンターの「ごみ箱を空にする」操作で行う処理。
・データはテーブルから論理的に削除されます。
・ただし、データベース内部で確保していた領域はすぐには解放されず、ファイルサイズ(ディスク上の物理サイズ)はそのままです。
👉 つまり「削除済みマークがついただけ」「空きスペースとして再利用可能」な状態。
データベースファイルサイズ削減:
・データベースファイルそのものを物理的に縮小する処理。
・データベースごとに専用のメンテナンスコマンドが必要。(後述参照)
・メンテナンスコマンドを実行すると、空き領域を詰め直してファイル自体を小さくできます。
👉 「PCのハードディスクをデフラグして物理容量を解放する」イメージに近いです。
例えるなら:
レコード削除
📒ノートのページはそのまま残っているが、内容だけが消えて白紙のスペースができる。
→ データベースでは「中身のレコードは消えるが、ファイルサイズ(ページ数)は変わらない」
データベースファイルサイズ削減
📒不要なページそのものを破り捨てることで、ノート自体が薄くなる。
→ データベースでは「空き領域ごと縮小して、ファイルサイズ自体が小さくなる」
上記を踏まえ、プリザンター上で削除を行った際の挙動について確認しましょう。
■ レコード削除の挙動
1. レコードを削除すると、ごみ箱に移動します。
- データベース上では「Results → Results_deleted」へ移動(期限付きは「Issues → Issues_deleted」)。
2. ごみ箱からレコードを削除すると、データベース上からも完全に削除されます。
ポイント:プリザンター画面上で「消えた」段階では、まだ*_deleted側に残っている可能性があります。完全に消すにはごみ箱を空にする(=*_deletedからも削除)ことが必要です。
■ テーブル削除の挙動
1. テーブルを削除すると、ごみ箱に移動します。
- データベース上では「Sites → Sites_deleted」へ移動。
- テーブルに登録されているレコードも「Results → Results_deleted」(期限付きなら「Issues → Issues_deleted」)へ移動。
2. ごみ箱からテーブルを削除すると、テーブル自体はデータベースから消えます。
- ただしテーブルに登録されているレコードは Results_deleted(期限付きは Issues_deleted)に残り、プリザンター画面からは見えません。
ポイント:「テーブルを完全削除」しても、レコードの削除履歴が*_deleted側に残る点に留意してください。
■ フォルダ削除の挙動
1. フォルダを削除すると、フォルダと配下のテーブルがごみ箱に移動します。
- データベース上では「Sites → Sites_deleted」へ。
- 配下テーブルも「Sites → Sites_deleted」へ。
- テーブルに登録されているレコードは「Results → Results_deleted」(期限付きは「Issues → Issues_deleted」)へ。
2. ごみ箱からフォルダを削除すると、フォルダとテーブルはデータベースから消えます。
- ただしテーブルは Sites_deleted に、レコードは Results_deleted(Issues_deleted)に残り、プリザンター画面からは見えません。
ポイント:フォルダ単位の削除は影響範囲が広く、*_deleted側に多くのデータが溜まりやすい点に留意してください。
■ レコード・テーブル・フォルダを確実に消す3つの方法
方法1:各テーブルでレコードを完全削除(ごみ箱も空に)してから、テーブルやフォルダを削除する
- この順序なら、レコードもテーブルもデータベース上から削除されます。
方法2:プリザンターのAPIで レコード一括削除 を実行する
- PhysicalDelete を指定したAPIにて、各サイトのデータを一括削除できます。大量データ時や運用自動化に有効です。
方法3:BackgroundService で定期的にごみ箱の削除を実行する
- DeleteTrashBox のパラメータを有効化にし、指定した期間(DeleteTrashBoxRetentionPeriodの日数)経過後にごみ箱の中身を毎日定時刻に削除します。
■ ごみ箱を空にしてもデータベースファイルサイズが小さくならない理由と対処
プリザンターのごみ箱を空にしても、データベースファイルサイズは自動で小さくなりません。データベースごとの性質に応じてメンテナンスが必要です。
✅ PostgreSQL
- 削除(または更新)された行は、物理的には直ちに消えず「無効(dead tuple)」として領域内に残ります。
- 実際にディスク上の保存領域(テーブルファイル)を小さくするには VACUUM FULL の実行が必要です。
👉 運用のコツ
- VACUUM FULLは排他ロックが発生しやすく、処理中は性能や可用性に影響します。業務時間外に計画実行することを推奨します。
- まずは通常のVACUUM/AutoVacuumで内部再利用を促し、ディスク上の保存領域の削減(物理縮小)が必要なタイミングのみVACUUM FULLを検討するのが現実的です。
- 実行前のバックアップ取得、対象テーブル選定(肥大化が著しいものから)、メンテナンス時間の確保がポイントです。
✅ SQL Server
- 削除や更新で空いた領域はデータベース内部で自動再利用されます。
- 物理ファイルのサイズ(=データベースファイルサイズ)自体を小さくしたい場合に限り、DBCC SHRINKDATABASEを計画的に実行します。
👉 運用のコツ
- 頻繁な縮小は断片化やその後の自動拡張を招き、かえってパフォーマンス低下を引き起こすことがあります。やむを得ない場合のみ、計画的に実行しましょう。
- 実行前のバックアップ、実行後のインデックスメンテナンス(再構築/再編成)も検討してください。
まとめ
いかがでしたか。
プリザンターの「削除」は、まず*_deletedへの移動であり、即座にデータベースファイルを縮小するわけではありません。
レコード/テーブル/フォルダでの削除の実態を把握し、完全に消したい場合は「レコード完全削除 → テーブル/フォルダ削除」の順序を徹底しましょう。
または、APIを使った一括削除、BackgroundServiceによるごみ箱の定期的な削除も活用しましょう。
データベースファイルサイズの縮小はデータベースの特性に依存します。PostgreSQLならVACUUM FULL、SQL Serverなら必要時のみDBCC SHRINKDATABASEを計画的に。
削除ポリシーとメンテナンス計画をセットで整えることが、安定運用とコスト最適化の近道です。
弊社では、プリザンター導入・活用に関して以下のサービスをご提供しています。
・年間サポート
・各種書籍
・帳票出力(Excel/PDF)支援パック
プリザンターの導入から開発・運用をあらゆる角度から全力サポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください!
☆☆☆
サービスの説明などをご希望の方は【 問い合わせフォーム 】よりお気軽にお問い合わせください。
☆☆☆
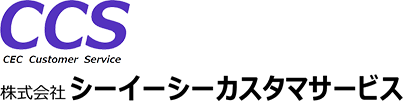
 MAIL
MAIL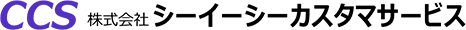


削除=容量減ではない!ごみ箱とデータベースファイルサイズの関係
こんにちは、シーイーシーカスタマサービスの森山です。
プリザンターで不要となったフォルダやレコードを削除した際に、「ディスク使用量が減っていない」と疑問に思ったことはありませんか?
この疑問は、プリザンターの削除の仕組みと、データベース(PostgreSQL/SQL Server)のファイル管理の違いを理解するとスッキリ解消します。
まずはプリザンターの構造とデータベース上の対応を整理しましょう。
■ プリザンター上の構成(サンプル)
- フォルダ > 記録テーブル > レコード
■ データベース上のテーブル対応
- フォルダ=Sites
- 記録テーブル=Sites
- レコード=Results(期限付きテーブルの場合は Issues)
- ごみ箱=各テーブル名+_deleted(例:Sites_deleted、Results_deleted、Issues_deleted)
※プリザンターでは、フォルダやテーブルといった「入れ物」全体を『サイト』として扱います。
このため、データベース上では「フォルダ」も「テーブル」も同じ「Sites」テーブルで管理されます。
ポイントはプリザンター上での「削除」操作は、まず「ごみ箱(*_deleted)」への移動であり、即座にデータベースファイルサイズを縮小しないことです。
ここを明確にしたうえで、次章でレコード/テーブル/フォルダ削除の挙動を具体的に確認し、最後にデータベースファイルサイズ削減の正しい手順をまとめます。
なお、本記事ではデータベース容量の話題を扱う際、混乱を避けるために「データベースファイルサイズ(ディスク上の物理サイズ)」と表記します。